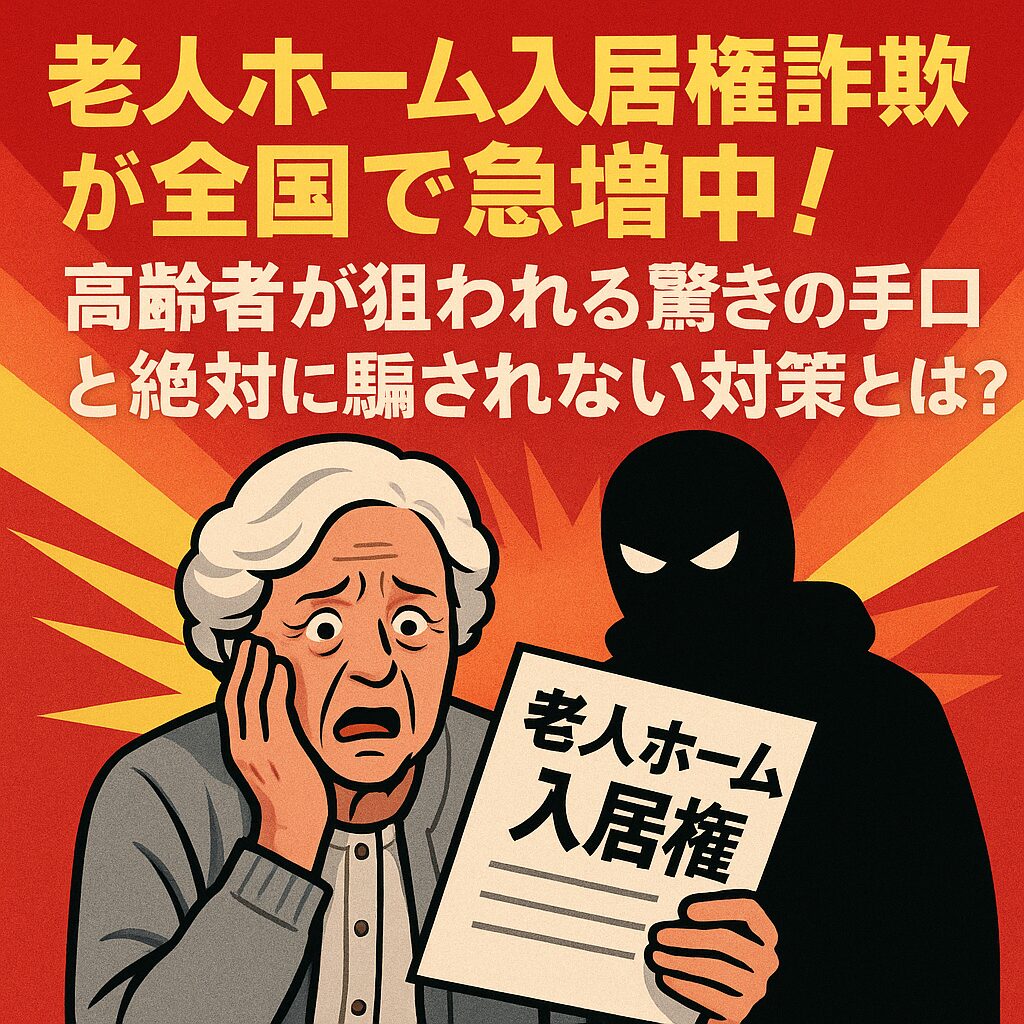「今だけ、優先的に人気の老人ホームにご案内できます」
――そんな言葉に安心してお金を振り込んだ直後、連絡がつかなくなる――。
いま、全国で老人ホーム入居権詐欺の被害が急増しています。
高齢化が進み、特に都市部では「入居待ち」が当たり前の時代。
その焦りに漬け込むように、詐欺グループが高齢者やその家族を標的にしているのです。
本記事では、実際に起きた詐欺の具体例を紹介しながら、
どうすれば被害を防げるか?
万が一騙されたらどうすればいいのか?
専門的な視点からわかりやすく解説していきます。
この記事を読むことで、あなたやご家族の大切な資産と未来を守るヒントが必ず見つかります。
- 実際に起きた「老人ホーム入居権詐欺」の事例
- 事例1:不意打ち訪問による即決勧誘(東京都・78歳女性)
- 事例2:電話一本で信用させる巧妙な偽担当者(大阪府・82歳男性)
- 事例3:入居権詐欺の三段構え(京都府・76歳女性)
- 事例4:訪問販売業者の強引なクロージング(神奈川県・75歳男性)
- 事例5:SNSの広告から誘導される詐欺(福岡県・68歳女性)
- 事例6:偽の公的機関名を騙る電話(北海道・80代男性)
- 事例7:紹介料名目で多額の現金を要求(埼玉県・76歳女性)
- 事例8:地域の老人会での偽説明会(岐阜県・70代男女複数)
- 事例9:新聞折込チラシの架空施設案内(広島県・72歳男性)
- 事例10:ネットの口コミを偽造したホームページ(愛媛県・65歳女性)
- 事例11:テレビCM風の偽動画に騙された(新潟県・70代男性)
- 事例12:介護専門誌の広告に偽情報(京都府・80代女性)
- 事例13:元職員を名乗る人物の勧誘(群馬県・75歳男性)
- 事例14:LINEでの勧誘(東京都・60代女性)
- 事例15:親族を装った人物からの紹介(兵庫県・85歳女性)
- 事例16:老人会を利用した集団勧誘(静岡県)
- 事例17:視察ツアーを装った勧誘旅行(長野県・70代夫婦)
- 事例18:偽ホームページで信用を得る(奈良県・68歳男性)
- 事例19:葬儀社からの紹介を装う(鹿児島県・82歳女性)
- 事例20:介護保険制度の誤情報を活用(富山県・76歳男性)
- 詐欺師がよく使う10の言葉に要注意!
- 騙されないための「鉄壁の防衛術」7選
- もし被害に遭ったら?すぐに取るべき対応
- まとめ:詐欺から身を守る最大の武器は「疑う力」
- あなたの家族を守るために今すぐできる3つのこと
実際に起きた「老人ホーム入居権詐欺」の事例
事例1:不意打ち訪問による即決勧誘(東京都・78歳女性)
ある晴れた午後、女性宅を訪ねてきた中年男性が「人気の老人ホームでキャンセルが出たので特別にご案内できます」と切り出しました。
彼は施設のパンフレットと見せかけたコピーを手に、「今日はここで契約すれば入居保証金が半額になります」と強引に迫ります。
焦った女性は、その場で現金50万円を手渡し契約書に署名。
後日、施設に確認したところ、その男性は関係者ではなく、契約自体が無効と判明。
事例2:電話一本で信用させる巧妙な偽担当者(大阪府・82歳男性)
電話で「人気老人ホームの空きが出ました。入居予約の手続きを進めるには保証金の先払いが必要です」と説明。
男性は「どんな施設ですか?」と尋ねると、具体的な介護サービスやスタッフの写真を送るなど詳細に説明。
安心して70万円を振り込むも、その後連絡が途絶え、振込先も実在しない口座だった。
事例3:入居権詐欺の三段構え(京都府・76歳女性)
76歳の女性宅に「おめでとうございます、抽選で老人ホームの入居権が当選しました」と電話があった。驚きつつも「申し込んだ記憶がない」と言うと、「地域の高齢者名簿から推薦されています」と説得された。入居予定はないと伝えると、後日別の人物から「ぜひその権利を譲ってほしい。30万円で買い取ります」と電話が来る。
信じ込んだ女性が了承すると、さらに数日後、今度は第三の人物から電話があり、「老人ホームの入居権を他人に譲渡することは詐欺にあたる犯罪です。すぐに調査を開始します。捜査を止めたいなら示談金が必要です」と脅される。恐怖心から指定口座に50万円を振り込んでしまった。
後に家族へ相談して詐欺と判明したが、振り込んだお金はすでに引き出されていた。3人が役割分担した三段階型の巧妙な詐欺だった。
事例4:訪問販売業者の強引なクロージング(神奈川県・75歳男性)
老人ホーム入居を検討していた男性宅に訪問した業者。
「今ならキャンセルが出ており、保証金を払えば確実に入居可能」と繰り返し説得。
業者は契約書をスマホで撮影し「後で送ります」と言い、男性は不安ながらも80万円を振り込でしまう。契約書は届かず、業者も連絡不能に。
事例5:SNSの広告から誘導される詐欺(福岡県・68歳女性)
Facebookで「高齢者向けの特別優遇プランあり」という広告をクリック。
公式を装ったページで電話番号を登録後、女性から電話が来て「特別な保証金が必要」と説明。振込後、電話番号は不通となり被害に気づく。SNS広告を使った詐欺は巧妙で注意が必要。
事例6:偽の公的機関名を騙る電話(北海道・80代男性)
「介護保険課です」と名乗る電話で「新しい入居優遇制度ができました。保証金を振り込めば利用可能」と案内。公的機関の名前に安心して60万円を振込でしまう。後日、自治体に問い合わせて詐欺だと判明。
事例7:紹介料名目で多額の現金を要求(埼玉県・76歳女性)
知人の紹介と称して訪問した男性が「人気施設の入居優先枠を確保するために紹介料が必要」と要求される。女性は30万円を現金で渡すも、後に紹介者と名乗った人物は架空であることが判明。
事例8:地域の老人会での偽説明会(岐阜県・70代男女複数)
老人会で開かれた介護施設の説明会で「特別優遇枠あり」と勧誘される。
参加者は資料請求料や申込金として計約100万円を支払うも、その団体は老人会とは無関係で詐欺と判明。
事例9:新聞折込チラシの架空施設案内(広島県・72歳男性)
新聞に入った「新規開設老人ホーム案内」のチラシを見て電話してしまう。「優先予約には保証金50万円が必要です」と案内され送金してしまう。その後、施設に問い合わせると実在せず、詐欺と発覚。
事例10:ネットの口コミを偽造したホームページ(愛媛県・65歳女性)
検索で見つけた人気施設のサイトにアクセス。口コミやスタッフ紹介が充実していたため信頼し、資料請求。後日保証金を振込むも、実は人気施設のホームページを模倣した偽サイトだった。
事例11:テレビCM風の偽動画に騙された(新潟県・70代男性)
一人暮らしの男性がYouTubeで見た「厚労省推進」と名乗る高齢者施設のCM風動画に興味を持ち、電話をかけると「地域限定の優先案内枠がある」と案内される。信頼感のある女性担当者から何度も電話が来て、契約書類は郵送で送ると言われる。入居保証金80万円を振り込んだ直後、電話番号が使われていない状態になってしまう。
事例12:介護専門誌の広告に偽情報(京都府・80代女性)
毎月愛読していた介護専門誌に「先着10名限定・新規開設ホーム入居案内」の広告を発見。誌面の信頼性から即電話し、「今ならキャンセル待ち枠をご案内できます」と言われ、振込先口座も印刷されていたため疑いを持たず40万円を支払ってしまう。しかし後日、雑誌編集部に問い合わせたところ、その広告自体が勝手に差し込まれた偽物と判明。
事例13:元職員を名乗る人物の勧誘(群馬県・75歳男性)
突然訪ねてきた中年男性が「以前あの老人ホームで勤務していた者」と語り、「紹介料をいただければ入居を優先できます」と巧みな営業トーク。立派なパンフレットや施設の写真を見せられ、60万円を現金で渡したが、施設に確認するとそのような人物は存在せず、当然入居枠もなかった。
事例14:LINEでの勧誘(東京都・60代女性)
趣味のサークルで知り合った知人のLINEグループに参加していた際、「最新空室速報」と記載されたリンクから入った公式風のアカウントに登録してしまう。
「入居優先には保証金30万円が必要」と言われ、手続き後にアカウントが突然削除されていた。LINE運営に通報するも、特定には至らず。
事例15:親族を装った人物からの紹介(兵庫県・85歳女性)
「息子さんの学生時代の知人です」と電話を受けた高齢女性。礼儀正しく「ご紹介でご案内できる特別施設があります」と説明され、疑いもせずに紹介手数料15万円を振り込んだ。しかし息子に確認すると、まったく知らない人物であることが判明。電話番号も非通知で追跡不能。
事例16:老人会を利用した集団勧誘(静岡県)
地域の老人会で実施された「健康講話」の後、配られたチラシに掲載された入居案内。
複数の会員が申込金や資料請求料と称してそれぞれ数十万円を振り込んだが、後日その団体が老人会とは無関係であることが発覚。チラシには存在しない住所、架空の連絡先が記載されていた。
事例17:視察ツアーを装った勧誘旅行(長野県・70代夫婦)
新聞折込チラシで見つけた「日帰り介護施設視察ツアー」。高齢者向け旅行とされ昼食付きで安心感があり申し込む。バス内で「この場で契約すれば入居優先」と迫られ、断ると集団で圧をかけられる状況に。恐怖と混乱で100万円の入居一時金を支払ったが、その施設は実在しておらず詐欺の被害に・・。
事例18:偽ホームページで信用を得る(奈良県・68歳男性)
検索でヒットした人気施設名のホームページをクリックし、資料請求フォームに個人情報を入力してしまう。届いた資料も精巧で信用し、電話連絡後に「入居保証金として50万円を事前に送金」と指示され実行。しかし、1か月経っても連絡がなく、調査したところ実在の施設ではない偽サイトと判明。
事例19:葬儀社からの紹介を装う(鹿児島県・82歳女性)
夫の葬儀後まもなく、「生前、ご主人様が相談していた老人ホームについてお話があります」と電話があった。信頼していた葬儀社の名前を出されたこともあり安心してしまい、紹介料と称した35万円を支払ったが、葬儀社に確認するとそのようなやり取りは存在せず、完全ななりすまし詐欺だった。
事例20:介護保険制度の誤情報を活用(富山県・76歳男性)
電話で「特別養護老人ホームの新制度により無料入居が可能」と案内される。「ただし制度申請に必要な保証金だけ事前に必要」と言われ、50万円を振り込んでしまった。行政に相談して初めて詐欺だと気づいたが、制度名も実在せず、連絡先も既に解約されていた。
詐欺師がよく使う10の言葉に要注意!
老人ホーム入居権詐欺をはじめ多くの詐欺は、ターゲットの心理を巧みに突く言葉で騙そうとします。以下の言葉を聞いたら、冷静になってください。
- 「今だけの特別な優先枠です」
→「今すぐ決めないと損する」と焦らせて冷静な判断を奪います。 - 「人気施設なのでキャンセル待ちが多いです」
→希少価値を強調し、「急がないと入れない」と思わせます。 - 「保証金は必ず返金されます」
→返金の約束はほぼ守られません。入金後は音信不通になるケースが多数。 - 「これは他には絶対教えていません」
→秘密の特別情報で信頼感を演出し、他者と話すのを阻止。 - 「お知り合いからの紹介です」
→親近感や安心感を与え、警戒心を解きます。 - 「行政も推奨している制度です」
→公的機関の名前を利用し、安心させる手口です。必ず自治体などで確認を。 - 「すぐに決断しないと権利が無くなります」
→急がせて冷静な検討を妨げます。 - 「契約書は後で郵送します」
→書面を手渡さず、契約の実態を曖昧にします。 - 「この話は内密にお願いします」
→相談や周囲への情報共有を妨害し、被害拡大を狙います。 - 「これは初回限定の特典です」
→限定性を強調して早期決断を迫ります。
騙されないための「鉄壁の防衛術」7選
1. 公式窓口に必ず直接問い合わせること
老人ホームの入居相談や契約の際は、必ずその施設の公式ホームページや電話番号を自分で調べ、直接連絡を取りましょう。
詐欺師は、架空の担当者や偽の窓口を装い電話や訪問をしてくることが多いです。
- 補足:自治体や厚生労働省の公式サイトも利用して、制度や入居条件の真偽を確認しましょう。
- 実例:ある被害者は、施設の紹介と言われて電話をしたところ、公式とは違う番号にかけていたため騙されました。
2. 契約書類は必ず書面で受け取り、内容をよく確認すること
口約束やメール・電話だけで契約を進めるのは非常に危険です。必ず契約書や重要事項説明書の原本を受け取り、専門家(家族や弁護士、消費生活センター)にも内容を確認してもらいましょう。
- 補足:契約書の記載に不明瞭な点や不自然な条項があれば、署名や押印を控えること。
- 実例:ある被害者は契約書が郵送されると言われて署名だけ先にしたが、契約書自体が詐欺だったため、契約が無効にできず多額の被害に。
3. 保証金・紹介料の事前振込は原則断ること
本物の老人ホームや公的機関は、保証金や紹介料の前払いを要求する際に必ず正式な書面と説明を伴います。
事前振込を急がせる場合は詐欺の可能性が高いため、冷静に断る勇気を持ちましょう。
- 補足:振込後に連絡が途絶えるのは典型的な詐欺の手口。送金前に必ず相手の身元を確認。
- 実例:訪問販売で急かされて保証金を振り込んだが、後日相手が行方不明になり返金は絶望的だったケース。
4. 訪問販売や電話勧誘は慎重に対応し、急な契約は避けること
詐欺師は「今だけ」や「すぐ契約しないと枠が無くなる」と急かしてきます。
急いで契約せず、家族や第三者と相談し、冷静に判断しましょう。
- 補足:訪問販売や電話勧誘では、知らない相手の話をすぐに信じないこと。
- 実例:ある高齢者は訪問販売員に強引に勧誘され契約。後で不審に思いキャンセルを試みたが、契約書がなくトラブルに。
5. 不審な連絡は家族・地域包括支援センター・消費生活センターに相談を
ひとりで判断せず、信頼できる家族や、地域包括支援センター、消費生活センターに相談しましょう。
専門機関は過去の詐欺情報や対応方法を持っており、被害を防ぐ力になります。
- 補足:自治体の高齢者支援窓口は無料相談が可能。詐欺被害は恥ずかしいことではありません。
- 実例:相談したことで詐欺だと気づき、振込を思いとどまったケースが多数報告されています。
6. 公的機関や介護施設の制度内容を正しく理解する
詐欺師は「厚労省の新制度で無料入居可能」など誤った情報を流します。
公的制度はホームページや窓口で正式な情報を確認し、疑わしい場合は役所に直接問い合わせましょう。
- 補足:公的機関名を使った詐称は巧妙。公式サイトのURLや連絡先を必ず自分で調べて確認。
- 実例:無料入居と聞いて振り込んだが、その制度自体が存在せず、詐欺と判明した例。
7. 契約前に必ず第三者(家族や専門家)に相談する
判断が難しいときは、必ず家族や介護の専門家、弁護士に相談して第三者の意見を聞くことが大切です。
一人で判断すると、詐欺師の心理的プレッシャーに負けやすくなります。
- 補足:特に大金が動く契約は、複数人で慎重に確認する習慣をつける。
- 実例:家族に相談して冷静になり、詐欺被害を免れたケースが多くあります。
この7つの防衛術を意識することで、老人ホーム入居権詐欺の被害を大幅に防げます。
詐欺は一瞬の隙をつくことが多いため、焦らず慎重な行動を心がけることが何より大切です。
もし被害に遭ったら?すぐに取るべき対応
- 警察署に被害届を提出する:事実関係や振込先口座を正確に伝える。
- 金融機関に連絡して振込停止や返金交渉を行う:可能な限り速やかに対応。
- 消費生活センターや弁護士に相談する:専門的なアドバイスと法的手続きを検討。
- 家族や知人に事情を説明し、サポートを得る:詐欺被害は一人で抱え込まず助けを。
まとめ:詐欺から身を守る最大の武器は「疑う力」
老人ホーム入居権詐欺は、巧妙かつ悪質な手口で高齢者の安心を奪う許し難い犯罪です。「特別」「今だけ」「急いで」などの言葉を聞いたら、まず疑いの目を持つこと。
家族や専門家に相談し、複数の情報を集めて判断しましょう。
被害を防ぐには「焦らない」「公式確認」「契約書の確認」が最重要。
この記事で紹介した事例と対策を活用し、ご家族やご自身の資産を守ってください。
あなたの家族を守るために今すぐできる3つのこと
- 家族で詐欺の手口を共有する
- 重要な契約は必ず複数人で確認する
- 不審な電話や訪問はすぐに自治体や警察に相談する